本編の実質的な終章である『帰り道』は激しいアクションシーンはないが、各要素に意味を持たせているように感じた。そのことについて「畦道と山道」「月の明かり」「星空」あたりに注目してあれこれ書きたいと思う。
畦道から山道へ
橙子&ベオとの争いが終わり平穏な日々がやってきたと思ったのもつかの間、草十郎は青子と共に彼女の実家に行くことになる。
青子の実家がある秋古城は、久遠寺邸のある三咲町よりは田舎だが、草十郎のいた「山」ほどは文明から遠ざかってはいない。二人は家のある山の上まで歩いていく。
靴には土の感触。
町とは違う柔らかさに、青子は懐かしさを感じている。
彼女にとっては、中学生時代まで毎日のように通った道だ。
道は長く、しばらくは畦道が続いている。
町のアスファルトとは違う感触の畦道から、昔を思い出す青子。

駅から続く畦道を歩きながら、青子にせっつかれて、橙子さんとの一件について聞く草十郎。ときに冗談を織り込む会話と、朗らかなBGMである「家路」が相まって、とても和やかだ。

道はいつしか、畦道から山道になっていた。
はげ山には街灯も民家もなく、明かりは星と月の光だけだった。
しかし人の手で作られた畦道から山道になると、会話の色調が変わる。青子が記憶を消されてしまうことを草十郎に打ち明けると、BGMはどこか不安げな「メインテーマ/眠り」になる。町の明かりは届かなくなり、星と月の光だけがあたりを照らす。
二人は山道へと進むことで、青子の実家へと近づくと同時に、草十郎のいた「山」の世界にも近づくことになる。どちらも二人の過去にまつわるもので、草十郎と青子の仮初の過去の場として機能する。
そして青子に問われ草十郎は過去を語りだす。
月と草十郎のいた世界
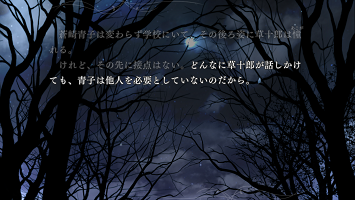
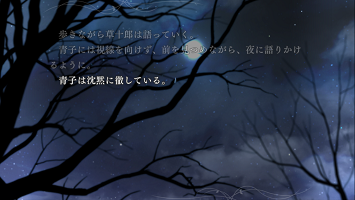
草十郎が過去を語っているときに何度も月が挿入される。

草十郎が山を下りるところまで話すと、青い月の明かりはしぼんで消える。彼の世界から、明かりは失われてしまう。
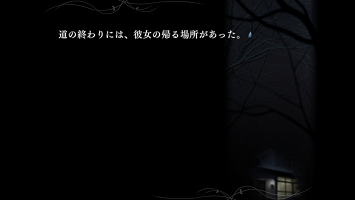
道の終わりには、彼女の帰る場所があった。
草十郎の話が終わると、消えた月の明かりと対比するように青子の家の明かりがあらわれる。それは帰る場所が変わらずにある青子と、そうではない草十郎の対比だ。つまり明かりは帰る場所(の象徴)として描写されている。

彼の棲んでいた世界は、ある意味で完成していた。
一つの事柄を成立させたければ、それ以外は何もない世界を作ればいい。
分かりやすく象徴的な構図。それ以外は何もない世界。
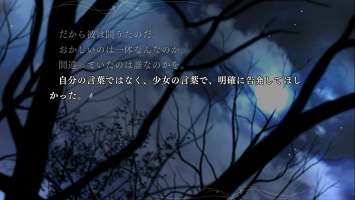
町の光が届かない山での月は、草十郎にとって帰る場所であった「山」の象徴だった。
ここでの会話以降、月が画面に映ることは無い。それは草十郎から月の明かりが失われてしまったからだ。
青子と草十郎の星空
その後、家に入る前に青子が、祖父との会話の後に草十郎が、それぞれ空を見上げる。上が青子、下が草十郎の見上げた星空だ。

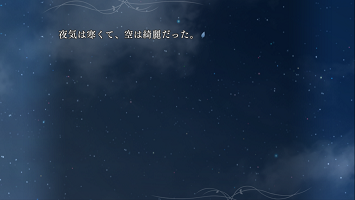
青子の見上げた星空は、青く澄んでいる。それに対して草十郎の見上げる星空はくすんでいる。メッセージウィンドウの有無もそれを強調している。
なぜ、草十郎には星空がくすんで見えているのだろうか?

「山ではね、蒼崎。星は本当に手が届きそうなんだ。届かないのは分かっていても、望めば本当に掴めそうなぐらい近いのに。都会の星は、そう思う事さえ許してくれない」
「……今まで、目に映るすべてを山と比べていた。こんな場所は、本当は嫌いだったんだ。今でも、正直なじめない。
でも、いつか比べるのは山になってしまうんだろう。自分は、こっちに下りてきてしまったんだから」*1
人里に下りてから見えるもの全てを「山」と比べていたことを告白する草十郎。
たしかに青子が魔法で顕現させた、(おそらくは)「山」の星空に比べると、彼女の見上げた澄んだ星空であっても手は届きそうにない。
その過去に見た「山」の星空と比べているから、今見上げる星空が草十郎にはくすんで見えている。
そして二人は帰るために再び山道を歩く。今度は、山道から畦道へとすすんでいく。
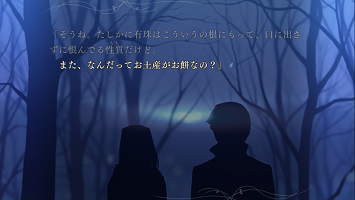
歩きながら有珠について会話する二人。その前方には、有珠が待っているだろう、そして今の草十郎の帰る場所である町の明かりが仄かにあらわれる。

不意に、草十郎は見上げたまま問いかけてきた。
「ひとつ聞きたいんだけど、君に後悔はあるのかな」
その問いに青子は答える。
「ないわよ、そんなの。だってそれをしない為に、今を頑張ってるんだもの。
後悔なんてのはね、草十郎。するものじゃなくて、無くしていく為にあるものなのよ」
草十郎が憧れる、これぞ蒼崎青子という答え。過去を美しくする為に生きている。
噛みしめるように、彼は万感の想いを葬った。
もう形も匂いも薄れている全てに、手を伸ばさず、手を振った。
「―――そうか。後悔も、無くなるものなのか」
ここで、これまでの全編を通して描かれてきた、草十郎の過去への執着は(ひとまずの)結末を迎える。

それを反映して、ここで見上げる草十郎の星空は、青子の見上げたものと同じ青く澄んだものになる。メッセージウィンドウも無い。それは「山」の星空とは比べずに空を見上げることが出来たからだ。彼は今の生活を受け入れ、過去に別れを告げる。
山道から畦道へ
二人は会話を続けながら、山道を歩く。
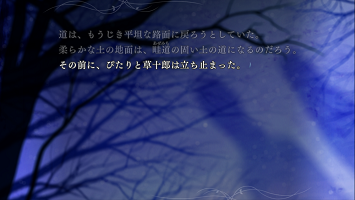
道は、もうじき平坦な路面に戻ろうとしていた。
柔らかな土の地面は、畦道の固い土の道になるのだろう。
その前に、ぴたりと草十郎は立ち止まった。
山道から畦道に変わる直前で草十郎は立ち止まり、青子に言う。
「おめでとう、蒼崎」
青子はわけも分からず目をまたたかせる。

「新しい年だ」
喜びに満ちた笑顔で、そう返答した。
新年の祝いの言葉とともに、山の木々を抜け、今の帰る場所である町の明かりが強調される。夜明けのようにも見えるそれは、草十郎にとっての新たな明かりだ。
過去に別れを告げたばかりの草十郎が、山道と畦道のまさに境界で、新年という新しいときを祝う。その前方は有珠の待つ町の明かりで輝いている。

なのに、たった少しの言葉だけで。
遠い昔に置いたままの、鐘の音の奇跡を信じていた少女が振り向いた気がしたのだ。
思い出の中で振り向く少女は、初めての振り袖なのに緊張の素振りもなくて、あんまり可愛くはなかったけれど。
それでも、鏡越しに微笑んでしまうだけの愛らしさはあったのだ。
青子の言葉によって草十郎は過去に残した後悔さえ変えられると知ったわけだが、それとは対照的に、草十郎の言葉によって青子は自分の中に変わっていなかった過去があったことに気が付かされる。
思えば、草十郎はしばしば青子(と有珠)に過去を思い起こさせる人物だった。部活決めでの一件や、草十郎が口にする「人殺しはいけないことだ」という言葉が彼女の捨てたはずの良心に訴えたように、ここでも青子に過去を振り返らせる。
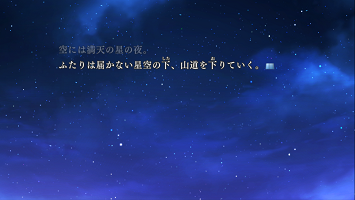
空には満天の星の夜。
ふたりは届かない星空の下、山道を下りていく。
星(空)=過去と捉えると、山に登ることは極めてシンプルな意味でほんのわずか過去に近づく行為だった。そしてつかの間、星々を仰ぎ見た二人は戻れはしない過去を後にして山を下りていく。その後エンディングと短い後日談が流れ、物語に幕が下りる。
